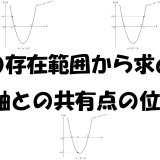数学の世界で、ものごとを整理して扱うために「集合」という考え方がある。
集合を理解することで、これからの論理や確率などの学習の出発点になる。
みんな集まれー!!
が、集合?

明確な基準がなく、範囲があいまいではっきりしないものは集合とは呼ばない。
集合を表すときは \[\{\:\:\:\:\}\] という波括弧(ブレイス)を使う。
・日本の都道府県(47個)
・1週間の曜日\(\{\)日, 月, 火, 水, 木, 金, 土\(\}\)
・大文字のアルファベット\(\{A,B,C,\cdots,Z\}\)
・10未満の正の偶数\(\{2,4,6,8\}\)
・日本のきれいな景色(景色は数えられず「きれい」の基準も人によって違う)
・暑い日(気温は地域ごとに異なり、何度以上を「暑い」とするか曖昧)
・かっこいいアルファベット(「かっこいい」の基準は人によって違う)
・大きい数(「大きい」がどこからか不明確)
こんな感じに、誰でも同じように決められるものを集合と呼び、人によって判断基準が変わるものは集合とは呼べない。
主観が入ると途端に集合じゃなくなる感じ?

集合をつくっている1つ1つのものを要素または元という。
高校数学までは大体「要素」って言う。
集まれー!
で集まったみんな1人1人はそれぞれ要素になる。
また、集合に「属する」と表現したりもする。
集合に属すれば要素、属さなければ要素ではない。
例えば、「4」は「10未満の正の偶数」という集合に属し、要素といえる。
「12」は「10未満の正の偶数」という集合には属さず、要素ではない。
数学で遭遇する対象を数学的対象と呼んだりする。
数学的対象は、数とか関係とか図形が多いかも。

要素は「\(∈\)」というボンボン帽子…包含記号を使って表す。
対象\(a\)が集合\(A\)の要素であるとき、 \[a∈A\] という感じに表して、「\(a\)は集合\(A\)に属する」って読む。
要素じゃないときは、 \[a∉A\] という感じに表して、「\(a\)は集合\(A\)に属さない」って読む。
例えば、「\(10\)未満の正の偶数\(A={0,2,4,6,8}\)」については、 \[4∈A\] \[12∉A\] こんな感じに表す。
\(a∈A\)は\(A∋a\)とも表せる。
集合\(A\)と対象\(a\)は必ず\(a∈A\)と\(a∉A\)のどちらか一方のみが成り立つ。
ある対象はある集合に対して「属する」か「属さない」かのどちらかが必ず成り立つということ。
覚え方は…まぁ、包含記号∈はボンボン帽子。
要素はボンボン。

ボンボン帽子を被ったらボンボンはその人の一部になるみたいなイメージでいいんじゃないかな。

ボンボンはその人の一部、ボンボンは要素みたいな。
ちょっとこじつけすぎ?

集合を表すときは \[\{\:\:\:\:\}\] という波括弧(ブレイス)を使う。
この波括弧の中身の表し方として「列挙」と「条件」がある。
列挙は、要素をすべて列挙する表現方法で、外延って呼んだりする。
例えば「\(10\)未満の正の偶数\(A\)」を

こんな感じに表す。
何が要素か一目瞭然だけど、要素の数が多いと不便だったり省略しなきゃいけなくなる。
条件は、要素の満たす条件を示す表現方法で、内包って呼んだりする。
基本的に縦線(バーティカルバー)で仕切り、左を要素の代表、右を条件で表す。
例えば「\(10\)未満の正の偶数\(A\)」を

こんな感じに表す。
大量の要素を一般化して表せるけど、具体的な要素が何なのか一目では分かりにくい。
また、集合の要素の個数が多かったり、無限に続く要素がある場合には、省略記号「\(\cdots\)」を使って

こんな感じに表すこともできる。
-1024x218.png)
| 範囲がはっきりしているものの集まり | |
| 集合をつくっている1つ1つのもの | |
| \(a\)は集合\(A\)に属する \(a\)は集合\(A\)の要素 |
-1024x691.png)
仲間に入るものを要素と呼んで、「\(a∈A\)」と書いて「\(a\)は集合\(A\)に属する」って読む。
集合は「全部書き出す(列挙)」か「条件で示す」で表す。
「\(∈\)ってなんだっけ?」ってなりがち。
 すうがくのいえ
すうがくのいえ