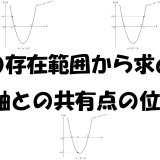符号というのは、正(プラス)か負(マイナス)のどちらか。
つまり、2つの数を比べたときプラスとマイナスの状態を異符号という。
符号が同じ場合は同符号っていう。
符号が一定であることを表す「定符号」というのがあるけど、それはまた別のお話。
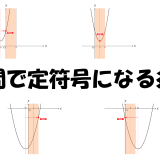 【2次不等式】区間で定符号になる条件
【2次不等式】区間で定符号になる条件

実数\(p,q\)の大小関係が\(p\)<\(q\)のとき、\(f(x)=ax^2+bx+c(a≠0)\)について\(f(p)\)と\(f(q)\)が異符号ならば、2次方程式\(f(x)=0\)は\(p\)<\(x\)<\(q\)の間に必ず実数解を1つもつという性質が成り立つ。
こんな感じ。長いので一つずつ分けると、
1.実数\(p,q\)の大小関係が\(p\)<\(q\)のとき
2.\(f(x)=ax^2+bx+c(a≠0)\)について\(f(p)\)と\(f(q)\)が異符号ならば
3.2次方程式\(f(x)=0\)は\(p\)<\(x\)<\(q\)の間に必ず実数解を1つもつ
という性質が成り立つので、グラフを交えながら順番に見ていく。
1.実数\(p,q\)の大小関係が\(p\)<\(q\)のとき
これはそのまま、2つの実数の大小関係を表す。

2.\(f(x)=ax^2+bx+c(a≠0)\)について\(f(p)\)と\(f(q)\)が異符号ならば
𝑥に\(p\)を代入すると\(f(p)\)、𝑥に\(q\)を代入すると\(f(q)\)となる。
代入した結果\(f(p)\)と\(f(q)\)の符号を比べたとき、
𝑥に\(p\)を代入すると\(f(p)\)、𝑥に\(q\)を代入すると\(f(q)\)となる。
代入した結果\(f(p)\)と\(f(q)\)の符号を比べたとき、
- \(f(p)\)はプラス、\(f(q)\)はマイナス
- \(f(p)\)はマイナス、\(f(q)\)はプラス

つまり、「\(f(p)\)と\(f(q)\)が異符号」というのは
3.2次方程式\(f(x)=0\)は\(p\)<\(x\)<\(q\)の間に必ず実数解を1つもつ
2次方程式\(f(x)=0\)は\(ax^2+bx+c=0\)のこと。
\(ax^2+bx+c=0\)の実数解が\(p\)と\(q\)の間に必ず1つあることを表す。
2次関数\(f(x)=ax^2+bx+c\)で考えると、必ず𝑥軸と交わるということ。
・\(a\)>\(0\)のとき

・\(a\)<\(0\)のとき

「\(f(p)\)>\(0,f(q)\)<\(0\)」のときも「\(f(p)\)<\(0,f(q)\)>\(0\)」のときも、2点\((p,f(p)),(q,f(q))\)を結ぶ連続した曲線は、区間\(p\)<\(x\)<\(q\)の間で\(f(x)=0\)を満たす点、つまり𝑥軸と交わる点をもつ。
なので、2次方程式\(f(x)=0\)は区間\(p\)<\(x\)<\(q\)の間に必ず実数解を1つもつことが分かる。
こんな感じに、連続な関数がある区間で定義され、区間の両端の関数値が異符号であるとき、その区間内に関数値が0になる点が少なくとも1つ存在することを中間値の定理という。
ここでは関数値が\(0\)になる点に注目したけど、関数値が\(0\)以外の任意の値に対しても同様に成り立つ。
以上から
実数\(p,q\)の大小関係が\(p\)<\(q\)のとき、\(f(x)=ax^2+bx+c(a≠0)\)について\(f(p)\)と\(f(q)\)が異符号ならば、2次方程式\(f(x)=0\)は\(p\)<\(x\)<\(q\)の間に必ず実数解を1つもつという性質が成り立つ。
ということが分かる。少し簡単にすると、
\(f(x)=ax^2+bx+c(a≠0)\)について
\(p\)<\(q,f(p)・f(q)\)<\(0\:\:\:\)のとき\(\:\:\:p\)<\(x\)<\(q\)の間に\(f(x)=0\)の実数解を必ず1つもつ
こんな感じ。
\(p\)<\(q,f(p)・f(q)\)<\(0\:\:\:\)のとき\(\:\:\:p\)<\(x\)<\(q\)の間に\(f(x)=0\)の実数解を必ず1つもつ

同符号は、「プラスとプラス」か「マイナスとマイナス」。
なので
下に凸\((a\)>\(0)\)の場合で考えてみると、


なので、同符号(\(f(p)・f(q)\)>\(0\))だと実数解をもつかどうか判断できない。

・区間①\(0\)<\(x\)<\(2\)

・区間②\(3\)<\(x\)<\(5\)

実際に\(f(x)=0\)を因数分解して解を求めてみると、

区間①\(0\)<\(x\)<\(2\)と区間②\(3\)<\(x\)<\(5\)の中に実数解があるということが分かる。
グラフで見てみると

こんな感じ。
-1024x218.png)
| 異なる符号ということ | |
| 同じ符号ということ | |
| 符号が一定ということ | |
| 連続な関数がある区間で定義され、区間の両端の関数値が異符号であるとき、その区間内に関数値が0になる点が少なくとも1つ存在する。関数値が0以外の任意の値に対しても同様に成り立つ。 |
-1024x691.png)
関数の値が、ある区間で異符号をとる場合、その区間内に実数解が存在する。
これは、連続な関数がある値をはさんで符号が変化するとき、その間に値をとる点があるという性質(中間値の定理)から分かる。
一方、関数が同符号をとる場合には、符号の変化がない以上、𝑥軸と交差する(=解がある)とは限らない。
こんな感じに、関数の符号に注目することで、2次方程式の解の存在範囲を把握できる。
2次方程式の性質を考えるときには、「異符号」という視点を一つのツールとして活用していきたい。
 すうがくのいえ
すうがくのいえ