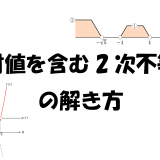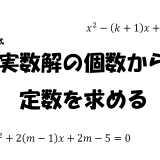絶対値を含む不等式と混同されやすいものとして、「絶対不等式」というのがある。
絶対不等式の問題は「どんな実数𝑥でも常に不等式が成り立つような条件」を考える。

解がすべての実数になる不等式は、「すべての実数\(x\)に対して不等式が成り立つ」「任意の実数\(x\)に対して不等式が成り立つ」のように表現されたりする。
つまり、どんな実数\(x\)を代入しても成り立つ不等式が絶対不等式ということ。
たとえば、どんな実数\(x\)を代入しても2次不等式\(ax^2+bx+c\)>\(0\)が成り立つということを考えてみる。
左辺を\(y\)と置いて、2次関数\(y=ax^2+bx+c\)のグラフを考えると、\(y\)>\(0\)はグラフ全体が常に\(x\)軸よりも上にあることになる。

どんな実数\(x\)を代入しても\(y\)>\(0\)となるので、どんな実数\(x\)を代入しても2次不等式\(ax^2+bx+c\)>\(0\)が成り立つ。
このグラフから、\(x\)軸との共有点がないことが分かるので、
 2次関数におけるx軸との共有点の求め方
2次不等式は
2次関数におけるx軸との共有点の求め方
2次不等式は\(ax^2+bx+c\)<\(0\)
\(ax^2+bx+c\)≧\(0\)
\(ax^2+bx+c\)≦\(0\)
それぞれがすべての実数\(x\)について成り立つ場合、
\(ax^2+bx+c\)<\(0\) のとき \(a\)<\(0\) かつ \(D\)<\(0\)
\(ax^2+bx+c\)≧\(0\) のとき \(a\)>\(0\) かつ \(D\)≦\(0\)
\(ax^2+bx+c\)≦\(0\) のとき \(a\)<\(0\) かつ \(D\)≦\(0\)

それも踏まえると、
\(ax^2+bx+c\)<\(0\)のとき「\(a=b=0\)かつ\(c\)<\(0\)」または「\(a\)<\(0\)かつ\(D\)<\(0\)」
\(ax^2+bx+c\)≧\(0\)のとき「\(a=b=0\)かつ\(c\)≧\(0\)」または「\(a\)>\(0\)かつ\(D\)≦\(0\)」
\(ax^2+bx+c\)≦\(0\)のとき「\(a=b=0\)かつ\(c\)≦\(0\)」または「\(a\)<\(0\)かつ\(D\)≦\(0\)」
これが絶対不等式の特徴。
実際に問題を解くときは、問題文を注意深く読まなくてはならない。

\(a\)>\(0\)は既に満たしており、\(D\)<\(0\)となるような定数\(k\)の値の範囲を求めれば良き。

\(-9\)<\(k\)<\(-1\)の範囲だと、下に凸のグラフが常に\(x\)軸よりも上側にあるので、\(y\)>\(0\)を満たすという感じ。
絶対不等式の特徴を覚えて解いていきたい。
-1024x197.png)
例題を解きながら、絶対不等式の特徴を確認していく。


すべての実数\(x\)に対して、2次不等式\(ax^2-2\sqrt{3}x+a+2\)≦\(0\)が成り立つので、
\(D\)≦\(0\)となるような定数\(a\)の値の範囲は



任意の実数\(x\)に対して、不等式\((a-1)x^2+(a-1)x-a\)<\(0\)が成り立つので、
\([1]a=b=0\)かつ\(c\)<\(0\)
または
\([2]a\)<\(0\)かつ\(D\)<\(0\)


-1024x218.png)
|
\(ax^2+bx+c\)>\(0\) \(ax^2+bx+c\)<\(0\) \(ax^2+bx+c\)≧\(0\) \(ax^2+bx+c\)≦\(0\) (\(a,b,c\)は定数、\(a≠0\)) |
|
| 解がすべての実数になる不等式 |
-1024x691.png)
理解するためには、やっぱりグラフから視覚的に捉えることが大事。
特に、不等式\(ax^2+bx+c\)>\(0\)で\(a=0\)の場合も含めて考えなくてはならないときは要注意。
不等号の種類や向きにも注意しながら、問題の意図をしっかりと読み解いていきたい。
 すうがくのいえ
すうがくのいえ